リニューアルのテーマ
ラフスケッチがボツになりました。しばらく落ち込みました。最初から「現在のタイトルを基に変えて欲しい」と言ってくれれば、アイディアを絞り出す苦労もせずに済んだろうし、時間を無駄にせずに済みました。人は初対面では言いたいことも言えないものですね。
ところが、一旦、言いにくい言葉を口にしてしまうと、そしてそれが相手に受け容れられると、言葉は溢れ出します。S氏も例外ではなく、私に「ボツ」を告げたあとは舌も滑らかになりきちんとした打ち合わせができました。
言葉が通じればいろんなものが見えてきます。ボツはストレスだったけれど、話し合いでモチベーションに変えることができました。そして、リニューアルのテーマがはっきりしました。
建築では新築よりも増改築の方が難しいといいます。リニューアルと言っても部分を直すものではありません。前のものよりも良くするためには新たに描くという地点に立ってテーマを見つめ直します。テーマの主なものを列記すると、
1.タイトルをどのようにして大きくするか。
2.S氏がこだわる「ミステリ」を活かす。
3.「ミステリマガジン」の文字の並び。「ミ」の形。
4.完成度を高めるための描き方、そして道具選び。

S氏がこだわった音引きのない「ミステリ」を印象付けることにもなる。
カタカナを克服する
1と2の問題はタイトルを『ミステリ』にすれば解決します。「ミステリ」を大きくして「マガジン」を小さくするという案です。
私はミステリ好きなので、友人との会話で『ミステリマガジン』が話題になると『ミステリマガジン』とは言わずに、「ミステリ」と言っていました。『SFマガジン』だって「SF」と言っていました。
戦前、戦中には雑誌を出したくても出せない時期がありました。編集者たちは鬱々としていたことでしょう。それが、終戦後間もない頃に雑誌を創刊するわけですから「マガジン」と表記することに編集者の矜恃と喜びが現れていたと思います。『ミステリ』ではなく『ミステリマガジン』でなくてはならなかった。しかし、以来、制作者が積み重ねてきた25年の歴史(業績)は制作者たちの思いを超えていました。世間には早川書房=「ミステリ(ー)」、早川書房=「SF」と言う認識は一般化していたと思います。
そういう理由から私は「マガジン」は目立たなくてもいいのではないかと思えていたのです。だから「ミステリ」を大きくして「マガジン」を小さく扱うと言う提案は問題なく受け容れてもらえると思っていました。しかし、案に相違してすぐには許可がでませんでした。
当時、Kくんから『SF(マガジン)』は自由にさせてもらえているけど、『ミステリ(マガジン)』は厳しいよと聞いていたので、ひたすら願う気持ちで許可を待ちました。結果はご覧の通り。編集長S氏の頑張りもあったでしょう。そして会社も少しずつ時代の動きを感じて変化を受け容れてくれているように思われました。
3は私の力量の問題です。これが一番難しかった。カタカナは奈良時代のお坊さんが漢文を和読するために漢字の一部を訓点として使っていたものです。平仮名の行書や草書などのように美しい造形を求めて育まれてきたモノではなく、機能性を重んじて使用されてきた結果の形だから文字としてはバランスが悪い。しかも、「ミ」以外の「テリマガジン」はすべて右上から左下への動きを持つ形です。「ミ」だけが逆の動きを持っているためにとてもバランスをとるのが難しいのです。逆に考えると「そこ」を克服すればいいロゴになると思いました。

リニューアル前のタイトルは「ミ」の両端が揃えてあります。そのために左上から右下への動きは封じられていますが、代わりに縦の線が強調されることになってしまいました。活字などの「ミ」と比べると不自然に見えます。推測ですが、左右を揃えたのは「ミ」だけが逆の動きを持っていることで並びが不自然に見える現象の解決策ではなかったでしょうか? 描いた人に聞いてみたいところです。
また、「ミ」を他の文字と同じ大きさの枠(左右幅)で揃えると文字は大きく見えます。だから横幅を狭くして小さく見えるようにしたのかもしれません。試行錯誤の跡を見る思いです。
私も試行錯誤を繰り返しました。3本の線の長さもミリ単位で模索して決めました。そして、その傾斜を水平に近づけると他の文字とのバランスが良くなるのを発見したのです。しかし、真横にしてしまうとエレメント(統一するための決まり)的に細い線にせざるを得なくなるので、それはできません。太さを保つには角度を持っている必要があります。2度、3度と変えながら一番いい形になる角度を模索しました。
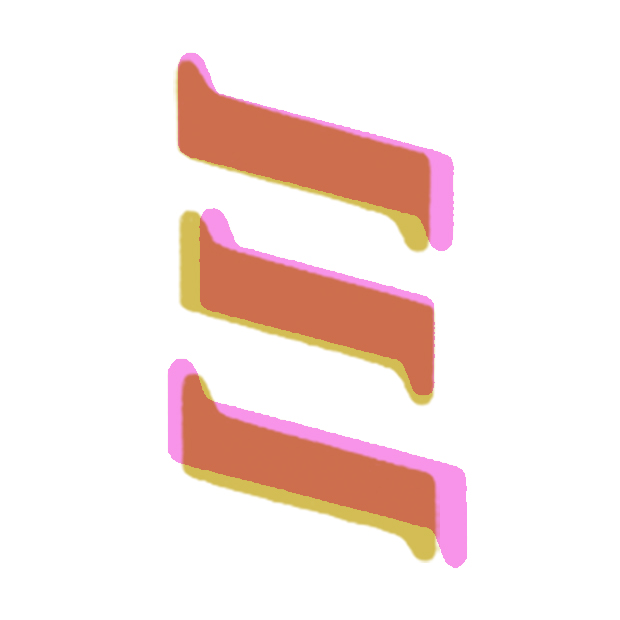
新しいロゴは左上から右下への傾斜がわずかに緩くなっている。
線を引くなら烏口が美しい
4は「道具」です。この当時(70年代半ば〜80年代)、デザイナーのほとんどがロットリングという製図用のペンを使うようになっていました。リニューアル前の『ミステリマガジン』のタイトルは、それよりもずっと前のものなので丸ペンで描かれていたのではないかと思われます。
用紙はケント紙のようなものではなかったでしょうか。ケント紙は画用紙の一種なので塗工紙(※)に比べると丸ペンで描いた場合はエッジのにじみが拡がりやすい。
私は烏口を使っていました。用紙も塗工紙です。当時一番美しく線が引ける組み合わせでした。
※【塗工紙】塗工紙は紙の表面を白色顔料などで滑らかに塗布したもの。塗料の量によってアート紙、コート紙、微塗工紙などがある。アート紙やコート紙などは美術書や本の表紙などで使われている。微塗工紙はチラシなどに使われることが多い。
※【ケント紙】ケント紙の「ケント」は、イギリスのケント地方で初めて作られたことにちなんだ名称。原材料もこの地のものであった。画用紙のひとつ。純白の上質紙でやや粗面。化学パルプが原料で図画・製図用紙、名刺用紙などに用いられていた。1970年代、学校の授業でポスターを作る時などはケント紙が使われていて、レタリングもケント紙であったために、デザイン業界でもケント紙を使っていた。塗工紙はややのちに出回る。

【線を引く道具】左から面相筆、丸ペン、烏口、ロットリング
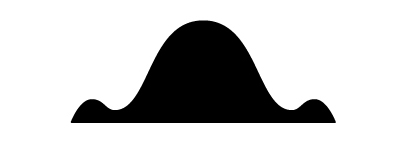
のイメージ(断面)。
烏口で線を引くと上下の刃の間のインクが盛りあげられる。ちょうど運動場にラインパウダー (line powder) で白線を引くような感じになる。インクが盛り上がると、製版写真撮影でフィルムにした場合には細い線でもくっきりと抜ける。

線を引いた場合】のイメージ(断面)。
丸ペンやロットリングで線を引くとペンの割れ目や穴を伝って流れ出たインクをペン先が引っ張ることになるので、用紙が引っ掻かれてインクがにじむ。フィルム撮りした場合にはカスレが出てくっきりとした線にならない場合がある。
印刷工程において「トンボ」と言われる線を引くには極細線(0.1mm以下)を使います。オフセット印刷の版下の作成でトンボを引く(描く)ための道具は筆から始まり、丸ペン、烏口、ロットリング、そして最近はデジタルと変遷してきました。
筆の場合は溝引き定規と面相筆を同時に操らなくてはならず、一般には難しい技術でした。しかも線の長さが1〜2cmであれば使えるけれど、長い極細線を一定の太さで引くには向きません。従って70年代にロットリングが出現するまでは丸ペンや烏口が主流でした。そしてそれらの中で繊細な線を安定的に表現するには烏口が優位であり、デザインの現場でロットリングが拡まっても緻密で正確な作業を必要とする製版、印刷の現場では烏口が使われていました。
版下に使われる台紙も製版、印刷の現場では塗工紙が一般的になっていました。デザインの現場でも少し遅れて、デザイナー向きの塗工紙が開発されるようになり画材店などに出回るようになりました。

面相筆の代わりに平筆を使ってベタ塗りもできる。
MAU造形ファイル アートとデザインの素材・道具・技法より
http://zokeifile.musabi.ac.jp/直定規/



